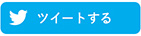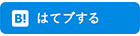「企業30年説」という言葉を耳にした人もおられるのではないはでしょうか。これは1983年に『日経ビジネス』が特集記事で初めて取り上げ、人口に大きな衝撃を与えました。つまり、人間に寿命があるように、企業にも寿命がありそれが30年というものでした。
それが事実なのかどうか定かではありませんが、帝国データバンクの統計データでは、企業の10年後の生存率は約7割、20年後に約半分になるとのことです。それだけ企業の生存競争は激しく、栄枯盛衰が繰り返されていることが見て取れます。
さて、企業が持続的に成長発展するためには、①時代を半歩先取りする成長エンジンを持つこと、②常に顧客満足を意識した製品やサービスを提供すること、③揺るぎない経営理念を持ちそれを社員に浸透させること、④それらを実行する人材の育成を図ること、が必要となります。
税理士業界の事業継承には税理士資格が必須条件なので、他の業界よりも困難だと言えます。日本税理士会連合会が公表した「第7回税理士実態調査報告書」では、後継者(後継者候補)がいないとの問いに84.5%がいないと答えています。さらに後継者不在の所長税理士に今後の見通しを問う設問では「自分の代で廃業する予定」が44.1%で最多でした。
幸いなことに、総合会計は創業者である私から、18歳ほど年齢が若い有能な後継者にスムーズに事業承継ができました。そして、バトンタッチ以後さらなる飛躍を遂げています。
ここで、総合会計が誕生した30年前のエピソードを少しだけ紹介します。『1995年阪神大震災が起きた年の4月1日、故郷の山口の地で開業しました。開業初日は、阪神大震災の影響で家財の荷物がまだ届かず、新幹線も動いていなかったので、夜行バスで到着する妻を防府駅まで迎えに行ったことを鮮明に覚えています。開業1年目は、借家の6畳の和室にカーペットを敷いて、大阪の自宅で使っていた古いパソコンと知り合いからもらったFAXやコピーを使って、今まで会計業務にまったく携わったことのない妻に手伝ってもらってスタートしました。もちろんお客様はまったくゼロだったので、知己を頼っていろいろなところへ挨拶回りをひたすらしました。業務連絡は、まだポケベルの時代でした。とにかく必死だったことが伝わったのか、三ヶ月目くらいから、「大阪から帰ってきたちょっと面白い税理士がいる」ということが評判になり、ご紹介のお客様がぼちぼち増えてきました。』
そして、筆舌に尽くしがたいほどのさまざまな紆余曲折を経てこの30年があっという間に経過しました。ものごとは螺旋状にしか発展しないとよく言われますが、まさに総合会計の歴史が螺旋状の歩みそのものでした。
さらに、10年、20年、50年へと未来に向かって総合会計がさらに発展することを切に願ってやみません。そしてそれを保証するには、事務所の全構成員が自分の持ち味を活かしながら、みんなで協力しあって民主的に運営することが必須条件ではないでしょうか。そして、必要なのは「量」を追求しながらも「質」の向上を常に図ることです。量と質の絶妙なバランス、確かに困難な課題ですが、果敢に挑戦することが求められています。