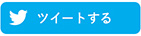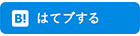先週、知人から広島の殻付き牡蛎とムキ牡蛎をいただきました。殻付き牡蛎は電子レンジで3分くらい、殻が空くまでチンしました。殻をこじ開け、レモン汁をかけて、醤油を垂らして食べるとこれが最高でした。ムキ牡蛎は牡蛎フライにして食べました。こちらも、シンプルにレモン汁をかけて食べました。なんとも言えない食感がたまりませんでした。
広島の名物と言えばお好み焼き、もみじまんじゅうなどが有名です。そして冬の時期の広島の牡蛎は最高です。広島では5月から翌年の3月ごろまで、牡蛎を生産していますが、その中でももっとも美味しい牡蛎を食べることが出来るのが、年明けで この時期は、牡蛎が冷たい海にさらされて、身が引き締まりずっしりとしたものになるからだと言われています。
やはり、季節ごとに旬のものを食べるのは最高です。この「旬」とは、自然の中でふつうに育てた野菜や果物がとれる季節や、魚がたくさんとれる季節のことで、食べ物によってその時期はちがいますが、一番おいしくて栄養もたっぷりです。また、たくさんとれるから、値段もお手頃です。
栄養豊富な旬の食べ物は、その時期に必要な栄養が豊富であることが多いです。例えば、夏に旬をむかえるトマトやキュウリは水分量が多く、熱中症予防や夏バテ対策になります。その一方で、ダイコンやホウレンソウといった冬に旬をむかえる野菜はビタミンやβカロテンが豊富で、体を温めたり、免疫力を高めて風邪を予防したりする効果が期待できます。
しかし、最近はハウス栽培や品種改良の進歩、外国からの輸入などにより、季節に関係なく多くの食材が手に入るようになりました。でも、旬の食べ物の本当のおいしさは、その時期でしか味わうことができません。
野菜や果物では、春が旬のものは、菜の花、たけのこ、ふき、春キャベツ、イチゴ、いよかんなど、夏が旬のものはトマト、きゅうり、なす、とうもろこし、オクラ、枝豆、メロンなど、秋が旬のものは、かぼちゃ、さつまいも、里芋、レンコン、ながいも、大根、栗、梨など、冬が旬のものは白菜、ほうれん草、かぶ、にんじん、春菊、みかんなどです。
魚では、春が旬のものは、真鯛、鰹、さより、鰆、めばる、鯵などです。夏が旬なものは、穴子、鮎、鰻、カンパチ、キス、ハモ、スズキなどです。秋が旬のものは、さんま、鰯、太刀魚、にしん、はたはたなどです。冬が旬のものは、あんこう、金目鯛、鱈、フグ、ぶり、ワカサギなどです。
さて、和食は各地の風土に合わせて生み出され、古くから親しまれてきた日本の伝統的な食文化です。もちろん旬な野菜や魚などの食材をふんだんに取り入れています。2013年には、未来に向けて保護・尊重すべき文化であるとして、ユネスコ無形文化遺産に登録されました。それにより、海外での人気や知名度が飛躍的に高まっています。訪日外国人(インバウンド)にも大好評です。ファストフードもたまには良いでしょうが、健康でおいしい和食の文化をそれぞれの家庭の食卓にもっと取り入れることが大切だと思います。